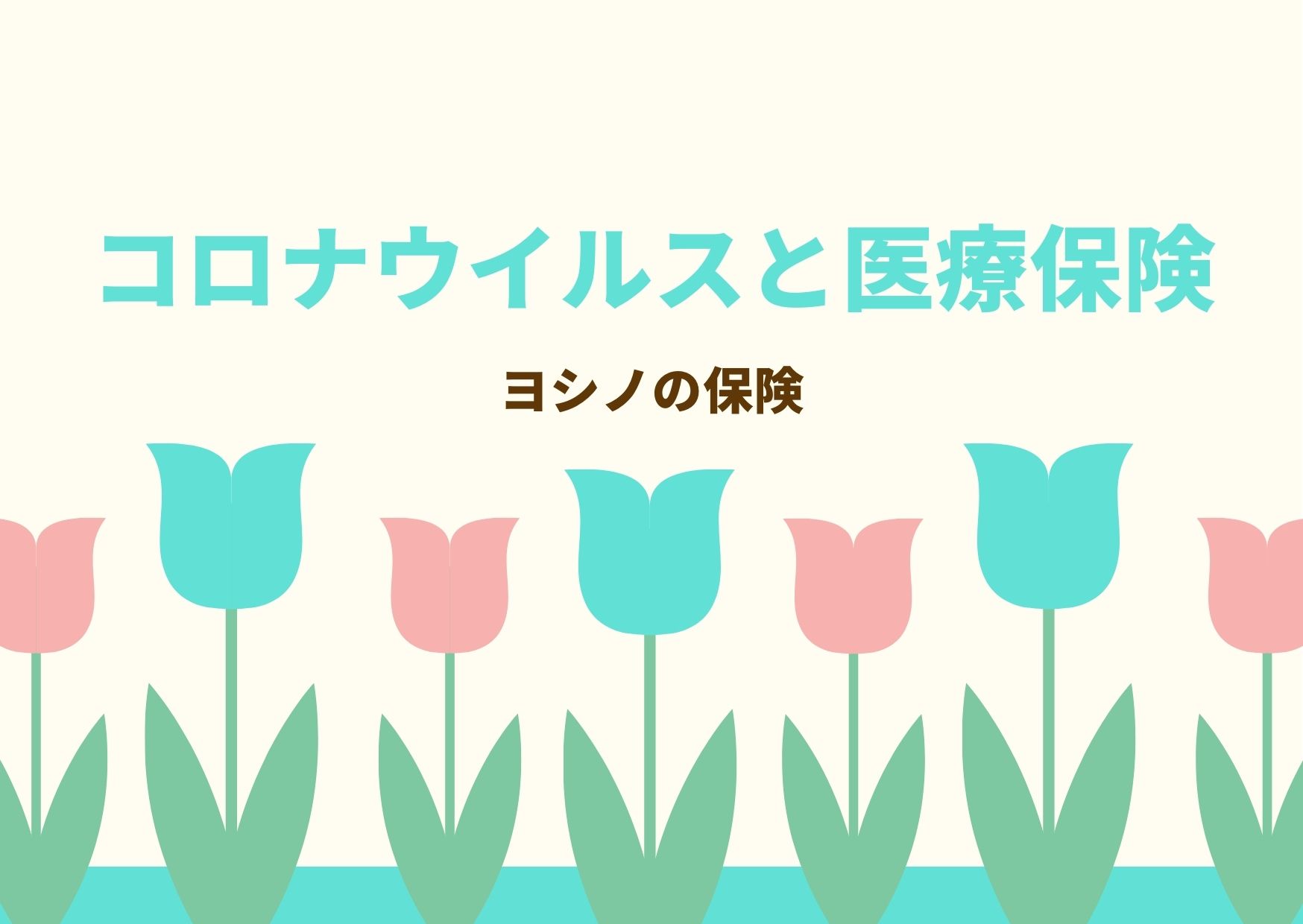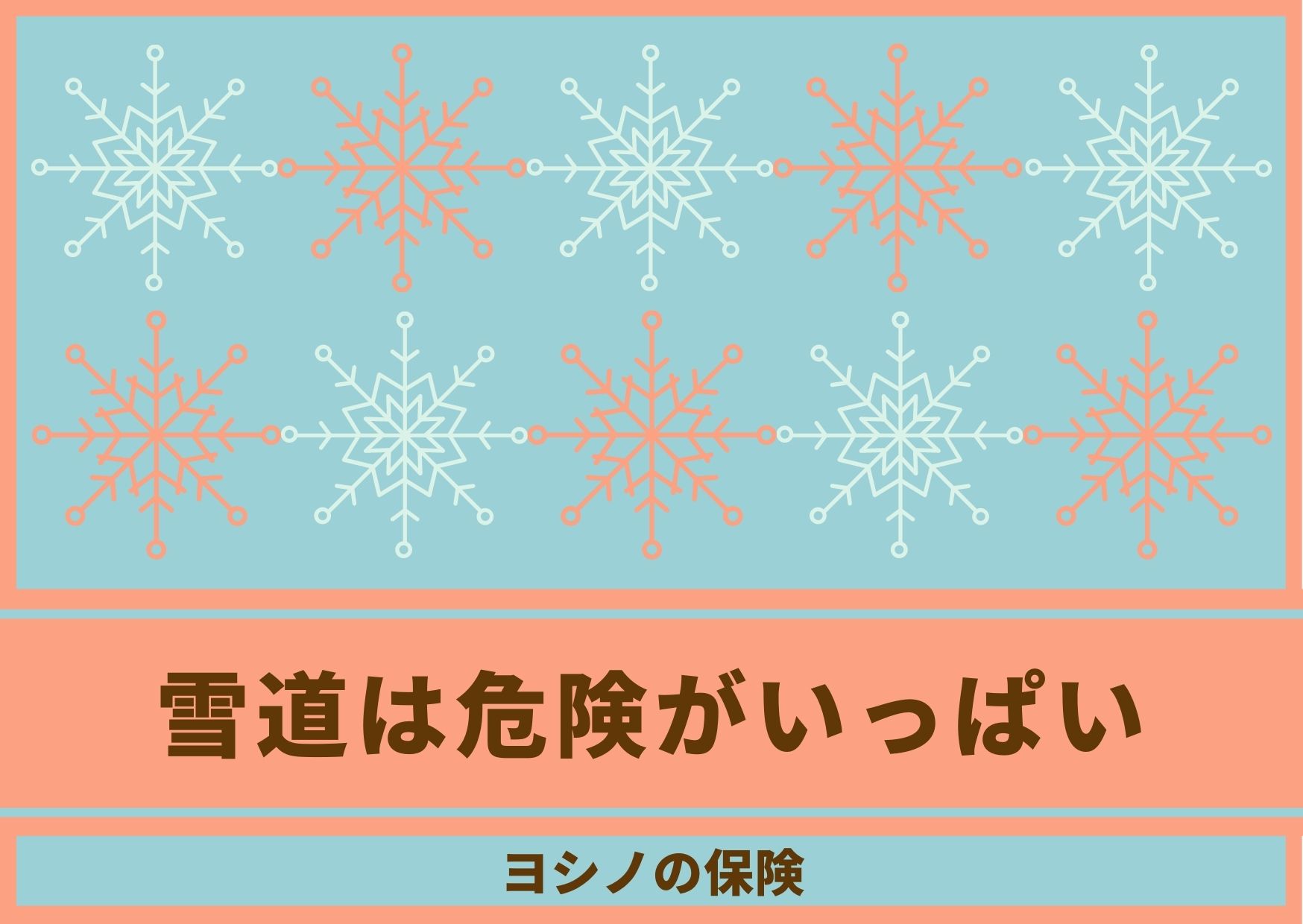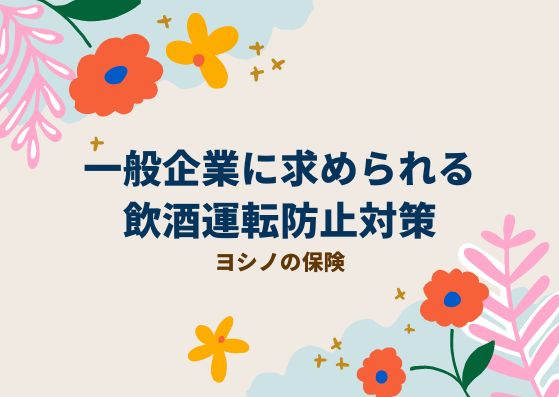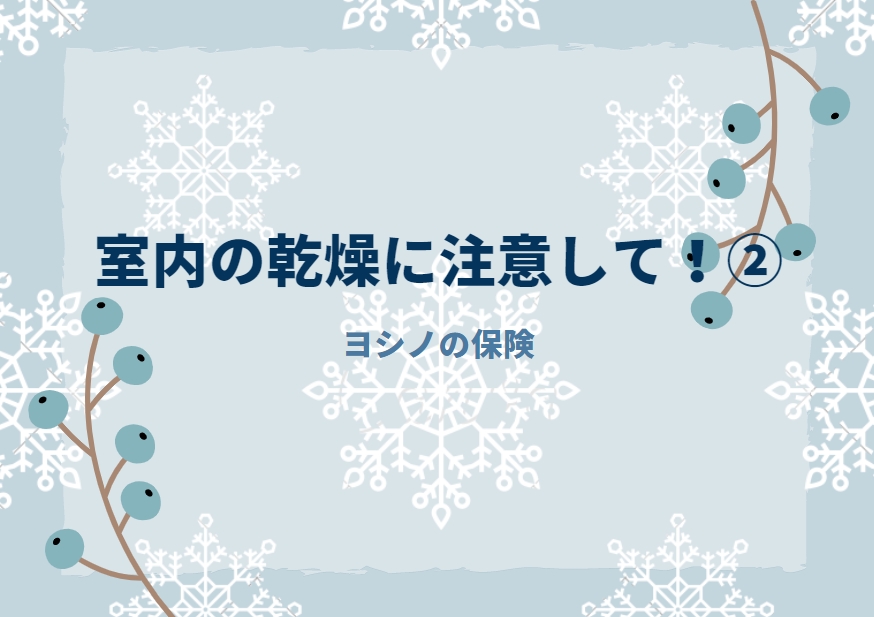皆さんこんにちは。
今回はコロナウイルスと医療保険についてお話します。
一昨年より猛威を振るっており、終息にはまだまだ時間がかかりそうですね。
そこで「コロナになった時に、自分が入っている保険っておりるの?」という
質問がありましたので回答したいと思います。
回答は「入っているタイプにもよりますが、基本的には下ります。」
まず初めに新型コロナウイルス感染症にかかった場合に、給付対象となる可能性があるのは「死亡・後遺障害」「入院日額」「疾病一時金」などとなります。
もちろん各社名称はさまざまですが、これは実際に病院施設に入院した場合もそうですが、ホテルなどの療養施設や自宅療養も含まれます。
ここまでで注意していただきたのは、医療保険のタイプには「〇〇日入院したら1日当たり〇〇円給付」というものと、「入院等にかかった実際の費用を給付」いうものもあります。
気を付けなければならないのは新型コロナウイルス感染症が、厚生労働省が「指定感染症」に指定したことにより、入院した際の医療費は基本的に公費で負担されます。
従って、実際の費用がないので前述の「かかった実際の費用を給付」というタイプでは、保険が下りない可能性があります。
保険の給付には、これも保険会社によって異なりますが
・新型コロナウイルス感染症の検査結果が「陽性」であることの証明
・宿泊療養(自宅療養)の療養開始日(陽性判明日)の記載がある市区町村や保健所発行の書類
(保健所や自治体が発行した宿泊・自宅療養証明書、就業制限通知書・就業制限解除通知書など)
などが必要になってきます。
新型コロナウイルス感染症が身近なものとなっている中で備えは重要となってきます。
保険会社によって補償内容や給付対象もさまざまです。
感染しないように気を付けて頂くのはもちろんですが感染してしまった場合も備えが必要ですね。
皆様、あけましておめでとうございます。
本年もヨシノブログのご愛顧のほど宜しくお願い申し上げます。
さて今回は、1月6日~7日において全国各地特に関東地方への降雪・寒波がありましたことによる雪災・凍結に関して話をしたいと思います。
関東圏にお住まいの方は積雪により大変だったと思いますが、斯く言う筆者もスタッドレスタイヤの用意をしておらず急遽チェーンを用意するなど朝晩はなかなか大変な思いをしました。
こうした災害において、主に「自動車保険」「火災保険」「傷害保険」がかかわってきます。
自動車保険・・・路面凍結を起因とする事故、自走不能によるロードアシスタントの利用など
火災保険 ・・・水道管の凍結による破損・水濡れ、積雪による家屋やカーポートの損害など
傷害保険 ・・・路面凍結により転倒によるけが、除雪中のけがなど
こう見てみますと降雪のよる保険のリスクは慣れない地域の方々は特に高く感じると思います。
こうした対策として
① 雪下ろしを行う前に、作業環境や天候に注意する。
雪下ろし作業は、家族や近所の人にも声をかけて、必ず2人以上で行うようにしましょう。気温上昇時は屋根の雪がゆるみやすいため、晴れの日ほど注意が必要です。低い屋根でも油断はせずに、建物の周りに雪を残し、面倒でも命綱とヘルメットを着用して雪下ろしを行うようにしましょう。
②カーポートの耐雪性を確認し、事前に雪下ろしをする。
自宅のカーポートがどれくらいの積雪に耐えられるか、耐雪性を事前にチェックしてみましょう。関東から東海、西日本にかけては、積雪20センチまで耐性があるタイプが多く、また雪が多い地域では、積雪50センチ以上の耐性があるタイプが使われています。カーポートの種類によって規定積雪に達する前に雪下ろしを行うようにしましょう。
③車の運転前に、路面やタイヤを確認する。
道路の降雪が1センチ以上になり、「白い光沢」に見えるときは表面が凍って滑りやすくなるため、車の運転は大変危険です。さらに路面が「透明または黒く」見えたときは、アイスバーンの危険があります。冬用タイヤの装着等、防滑措置を取り、スピードダウン、車間距離の確保を心掛けましょう。
④雪道では、転びにくい歩き方をする。
雪道を歩くときは、ペンギンのように歩幅を小さくして歩くようにすると、体の揺れが小さくなり、転びにくくなります。また、つるつると滑りやすい路面では、滑りにくい靴底の履物を選び、できるだけ靴の裏全体を路面に付けるようにして、体の重心をやや前において歩くようにしましょう。
保険としての対策はもちろんとして、日常から準備を心がけるのは大切ですね。
みなさんこんにちは。
あっという間にクリスマスが過ぎ、今年も残すところあと僅かとなしましたね!
昨年同様コロナ渦なので年末年始は車での帰省を考えている方も多いのではないでしょうか?
最近は急な寒波に襲われ積雪する地域もふえてきましてね。
そこで今回は雪道での注意点と予防策をご紹介いたします!
まずは雪道での注意点
・雪道を走るにあたっては必ず スタッドレスタイヤ や チェーン を装着する!
ノーマルタイヤでの雪道走行は大変危険です。
・車間距離をあけて走行、停止をする!
雪道は思った以上に滑るので余裕をもって走行を心がけましょう。
・発進時のアクセルはゆっくり発進で、ブレーキも余裕をもって!
雪道での急発進・急停止はアスファルトの道路以上に大変危険です。
急発進はタイヤの空回りを起こしやすく、急停止はスリップ事故になりかねません。
雪道の中には積雪の上だけではなく、
アイスバーン やアスファルトの道路に見えるが実は路面凍結している ブラックバーン
など様々な危険があります。
ここからは予防策のご紹介です
雪道を走る前に用意しておいた方がいいもの
・スタッドレスタイヤ、タイヤチェーン、ジャッキ
スタッドレスタイヤを装着していてもタイヤチェーンの装着は大切です!
・寒冷地仕様のウォッシャー液
通常のウォッシャー液では凍結する恐れがあるので
寒冷地仕様のものに入れ替えておくとよいでしょう!
・毛布や防寒具
雪道ではロードアシスタンスの到着も遅れる場合があるので
急なトラブルでエンジンがかからない状況など、寒さをしのぐ手段として
備えておくとよいでしょう!
あまり雪の降らない地域やめったに雪道を走らない方は、
レンタカーという選択肢もあります!
レンタカーのほとんどは冬季にスタッドレスタイヤに履き替えていることが多く
軽い雪道ならそのまま走ることができます。
もし積雪の多い地域を走る場合でもレンタル時に相談してみるといいでしょう!
くれぐれも帰省の際はお気をつけてください。
今日で筆者は仕事納めとなります。
今年も一年、保険ブログをご覧いただき誠にありがとうございました。
これからも皆様のお役に立てる情報を発進していきたいと思いますので
来年もよろしくお願いいたします。
みなさん、こんにちわ!
12月に入り、「もう師走かぁ、、」とあっという間の1年だったと感じてしまう筆者です。
緊急事態宣言やまん延防止対策が解かれた中での年末は会社などで忘年会など宴席が行われることが多いことでしょう。
そこで一般企業に求められる飲酒運転防止対策について考えてみましょう。
今年6月末、千葉県八街市にて小学生の列にトラックが突っ込み5人が死傷する悲惨な事故が発生し、社会に大きな影響を及ぼしました。
これにより道路交通法の一部が改正し、一般事業者に対して運転者へのアルコールチェックが義務化となりました。(2022.10.1施行)
運転事業者に分類されなくとも自動車の運転が不可欠である一般事業者においても交通事故発生時に問われることになる責任を理解する必要があります。
まず交通事故を起こした場合の企業責任(法令に基づく責任)を見ていきましょう。
1、刑事責任
道路交通法第75条において「自動車の使用者等(事業においてはおおむね管理職のことを指す)は運転者に対して、酒酔い運転・酒気帯び運転、無免許運転他などに示す行為を下命・容認してはならない」としている。
2、行政責任
警察や公安委員会などの行政当局が行う処分に従わなければならない責任とし、社有車の使用制限命令や安全運転管理者の解任命令などがある。そして202210.1施行された道交法「アルコール検査機を用いて確認を行うこと」もここに含まれます。
3、民事責任
交通事故の場合、加害者が被害者に対して行う民事上での賠償責任を指す。企業には「使用者責任」があり企業(使用者)の従業員が業務中に第三者に損害を与えた場合、従業員だけでなく企業側も損害賠償責任を問われる。また企業等が事故を起こした車両の「運転供用者」 であるとされた場合にも運転共用者責任が問われることもあり、例えば従業員による社用車の無断使用や他人への社用車貸与時の事故なども企業側に責任が問われる。これにより「従業員が勝手に使用した」など理由が通じないことを示していると言えます。
一般企業がとるべき飲酒運防止対策として国土交通省が事業用自動車総合安全プラン2025というものを策定している、これは一般事業者においても参考となりますのでご覧になってください。
https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha02_hh_000450.html
SNSなどで誤情報を含め容易に第3者へ拡散する時代です。
起きてしまった事故において会社の道義的責任も含め信用失墜につながらないよう安全管理方法を検討・実施されたいですね。
みなさんこんにちは。
今回は乾燥、火事の予防と対策についてご紹介します!
冬は外気の乾燥に加えて、室内では暖房器具を使用するため
室内では思っている以上に乾燥しています。
ですので、まずは室内の加湿が大切です!
夏場は湿気が多くて暑さを感じますがその分火災は少ないです。
反対に、冬は乾燥によって寒さを感じるのに加えて火災も起こりやすいです。
よって、冬場の加湿は防災対策に加えて暖房効率を高める効果があるので最適と思われます。
簡単な方法として、濡れたバスタオルを部屋にかけておくだけでも加湿器の役割をしてくれます!
しかし、外との寒暖差で窓付近などに結露も起こりやすくなすので、カビ対策も忘れずに!
火災の原因としてもっとも多いのが、年間を通して“放火”と言われています。
冬は火が燃え広がりやすく、放火件数も増加するそうです。
そこで、放火犯に狙われない対策として
- 家の周りに燃えるごみなどの燃えやすいものを置かない。
- 物置や車庫は他人が入れないようにする。
など、放火の標的にならないように気を付けましょう。
最後に、備えておいた方がためになる防災グッズを紹介します!
まずは、住宅用消火器。
消火器というと赤くてホースの付いた缶が思い浮かびますが、
最近では消火器も様々な形状のものがあるので
ご家庭に合った消火器を探してみるといいかもしれませんね。
住宅用消火器は有効期間がおおむね5年となっていますので、
現在お持ちの方は確認してみてはいかがでしょう。
次に、住宅用火災警報器。
火災報知器の設置は平成18年6月以降に着工した住宅に義務づけられていますが、
それ以前に建てられた住宅などでは設置されていないご家庭が今でも多いと言われています。
火災報知器は取付工事が必要なものから、2,000円前後の自分で取り付け可能なものもあるので
設置がまだの方は是非とも検討して下さい。
5 / 11« 先頭«...34567...10...»最後 »