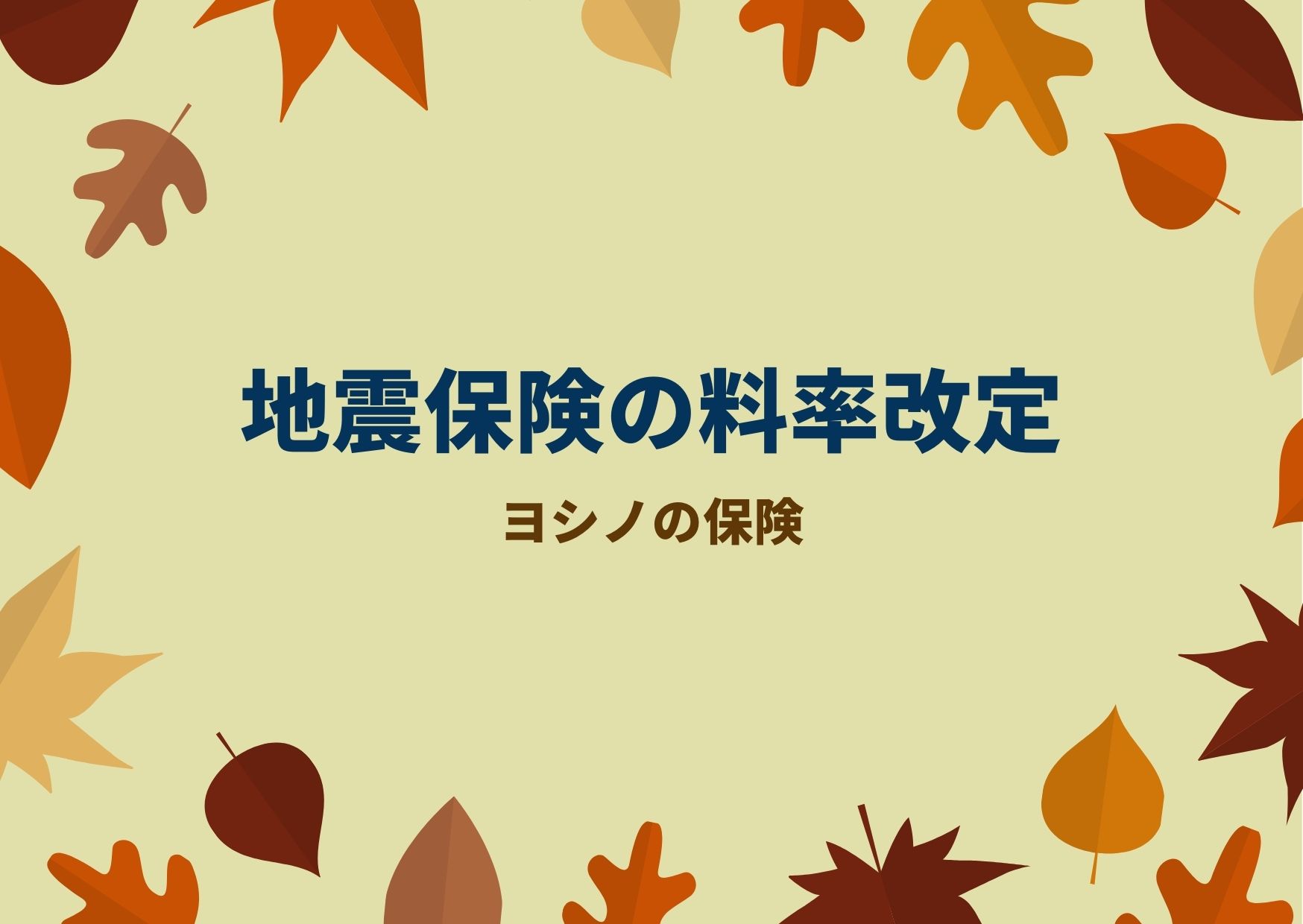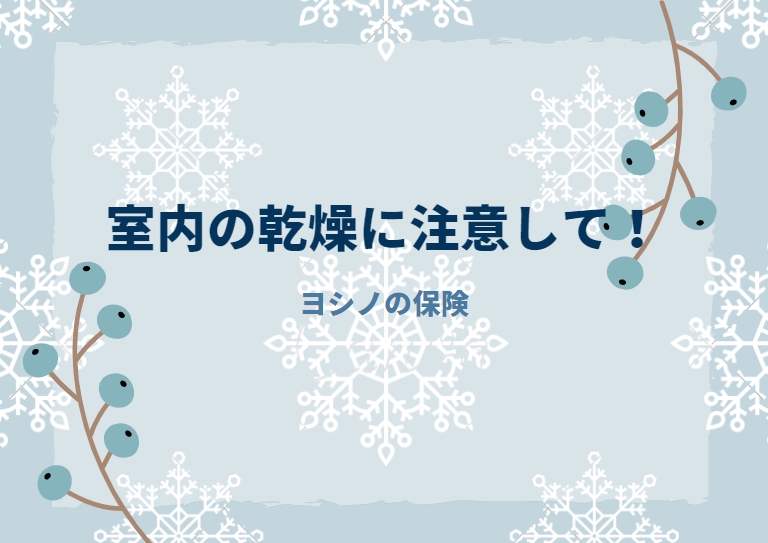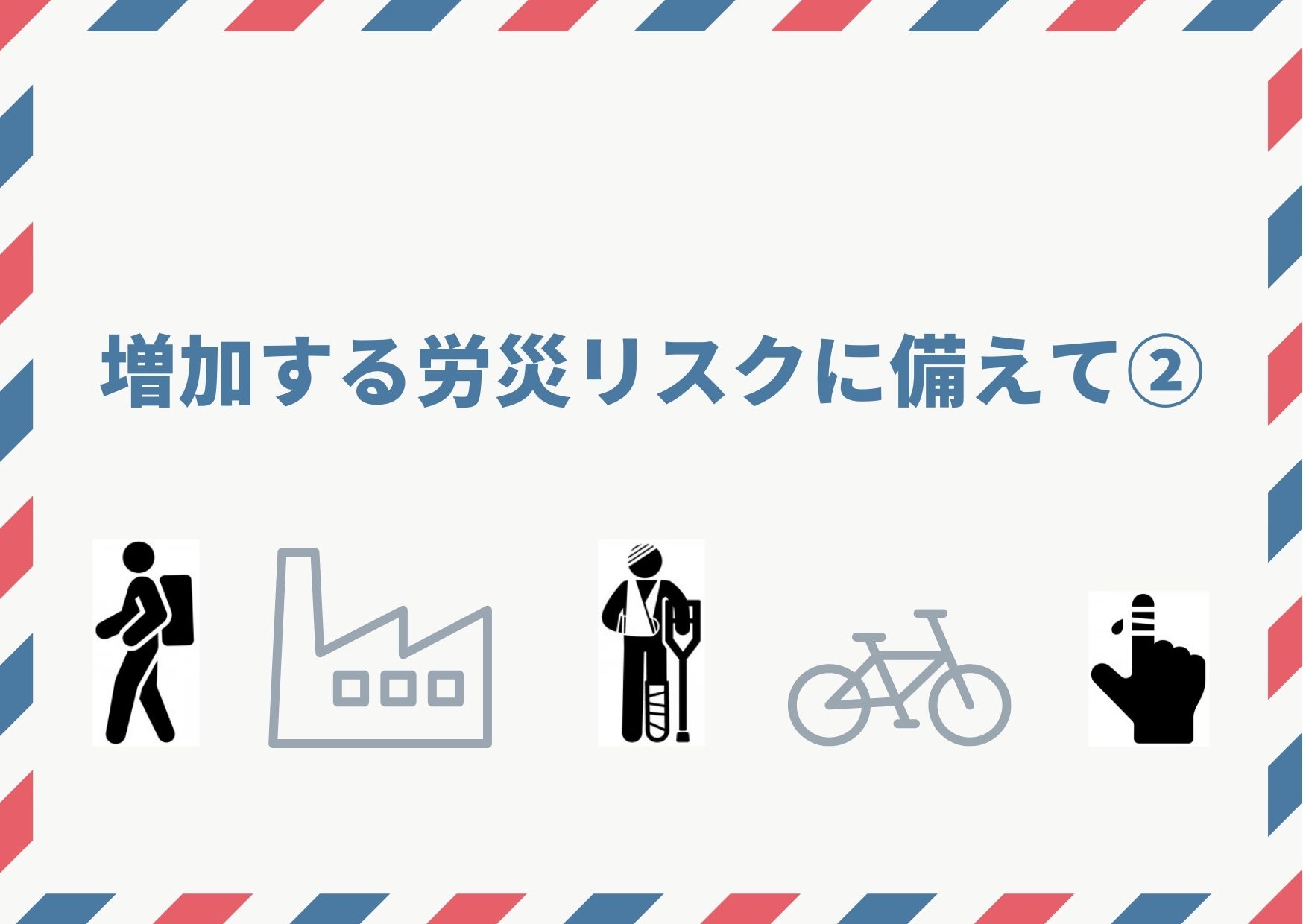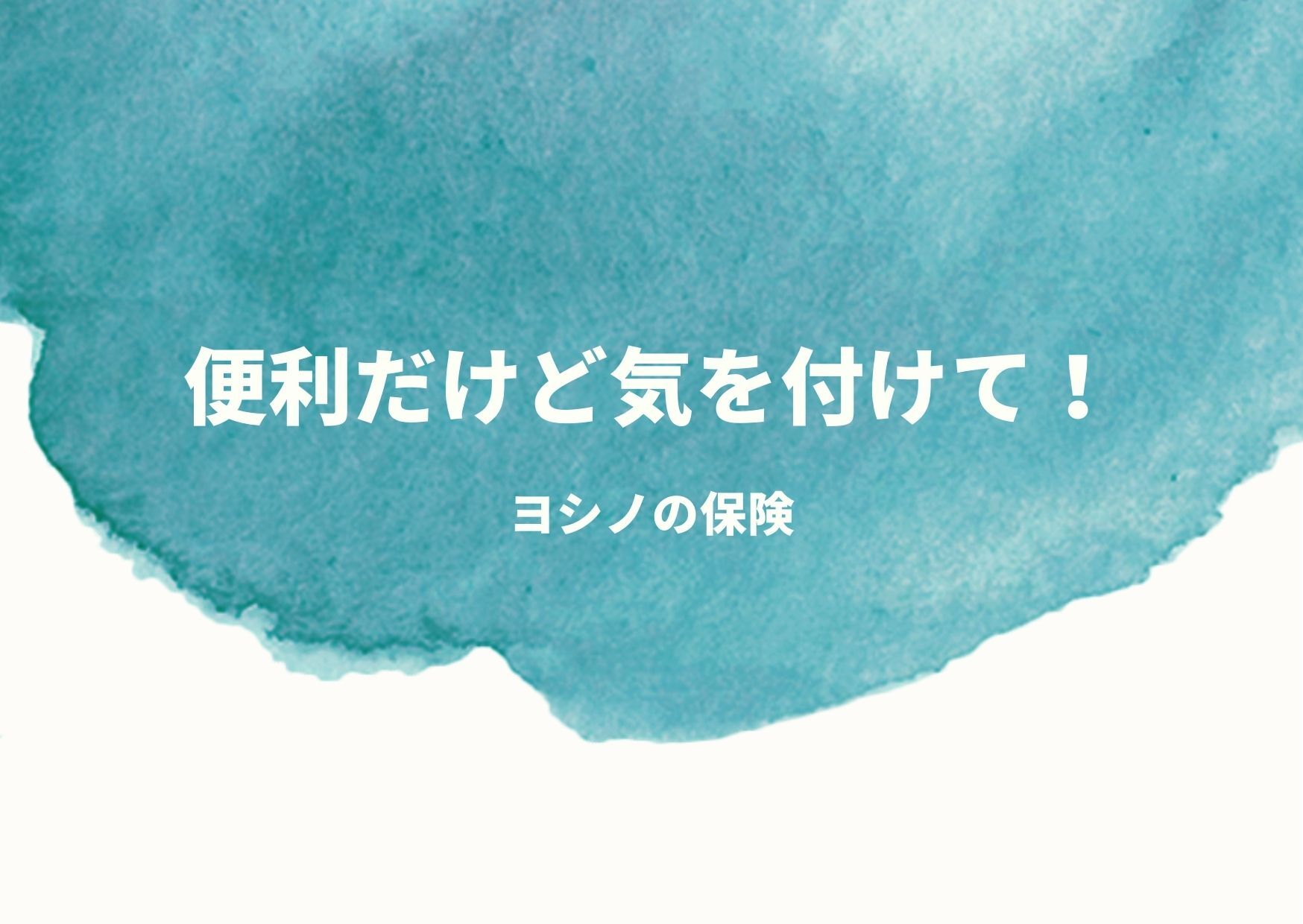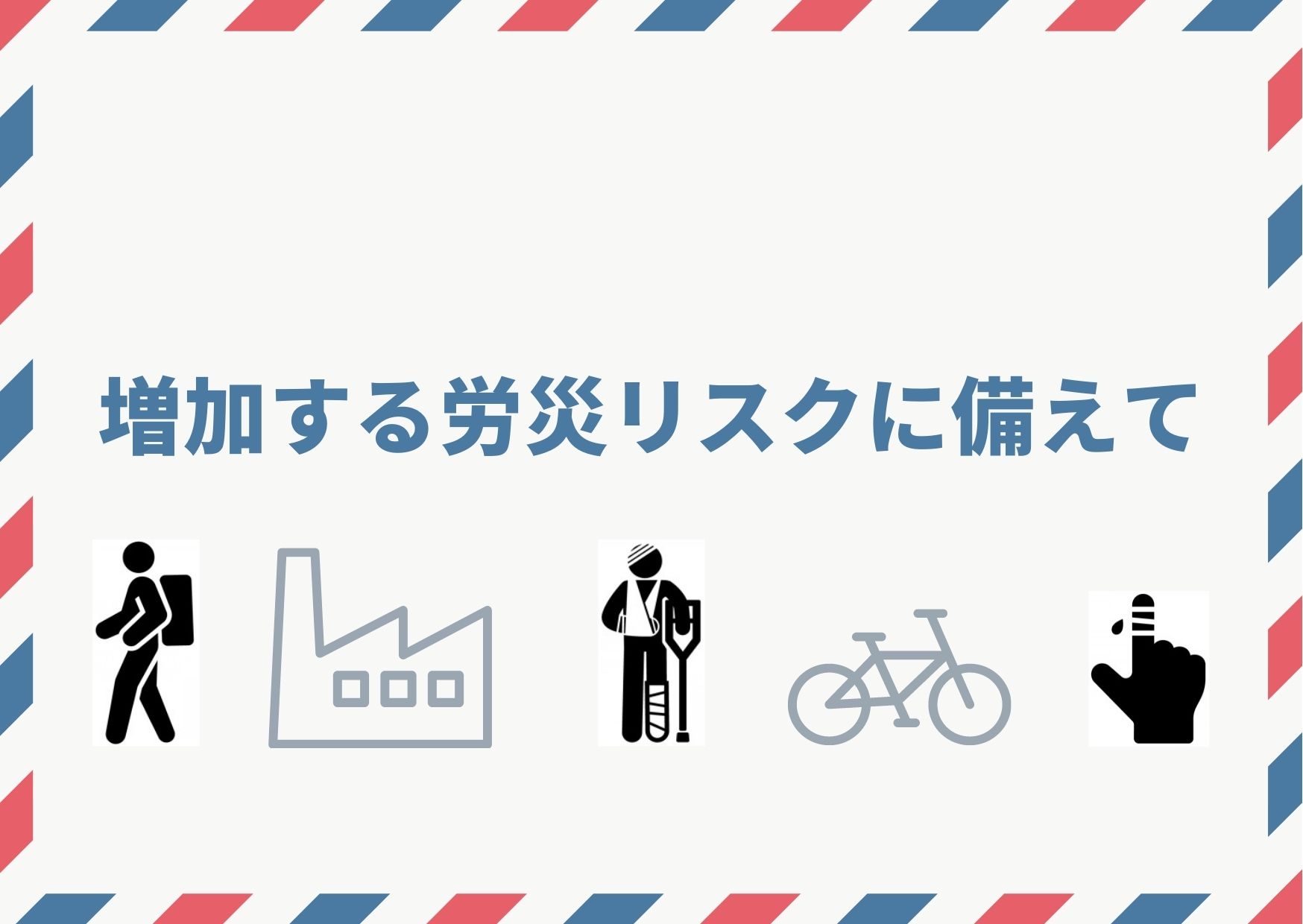みなさんこんにちは。
11月に入り今年も残すところあと2か月となりましたね。
さて、表題の通り地震保険が2022年10月以降に料率改定となります。
この改定によって何が変わるかを見ていきましょう。
・全国平均で0.7%安くなる
・長期契約の割引率の減少
となります。
各項目を詳しく説明しますと
まず全国平均で0.7%安くなるということですが、実は、、、
①安くなる地域もあれば逆に高くになる地域もある
②家の構造(耐火・非耐火)によって割引増率が変わってくる
となってます。
家の構造は大きく耐火と非耐火に分かれており
耐火構造とは、マンションなどのコンクリート造りや鉄骨で作られた建物のことを指し
多くの県が約1、4%~1、7%ほどの割引となります。
また全国で高い保険料水準でもある東京・神奈川・千葉・静岡の4都県は料率据え置きとなります。
残念ながら高くなる県もあります。福島県は約20%、茨城県・埼玉県・徳島県・高知県は30%ほど
上がります。
非耐火構造とは、住宅で一番多い木造建築物を指し
多くの県が約8%~9%ほど割引になります。
据え置きだった東京・神奈川・千葉・静岡の4都県も約2、5%ほど安くなります。
残念ながら茨城県・埼玉県は約12%の値上げとなります。
長期契約の割引率の減少とは
地震保険も火災保険と同様に最長5年まで契約でき
もちろん長期間に掛けるほうが1年更新と比べると保険料が安くなります
その長期契約の割引率が下がったことになります。
しかしながら保険料率自体は国が運営している損害保険料率算出機構が設定しており
近年では値上げ傾向がずっと続いてきました。
長期契約の方が契約期間中の値上げの影響を受けないというメリットを考えると
今まで通り長期契約のほうがオススメ出来ると思います。
地震保険の全国付帯率は68、3%(損害保険料率算出機構2020度より抜粋)となっており
大規模地震に備え、多くの人が地震保険を掛けていると思います。
少しでも保険料が下がり、家計の助けとなって欲しいですね。
みなさんこんにちは。
最近はめっきりと寒くなってきました。
つい、2週間ぐらい前まで昼間は半袖で過ごせる気温だったのに
秋を通り越して一気に冬が来たような感じですね、、、
寒くなると同時にやってくるのが乾燥です。
そして乾燥する時期に気を付けたいのが“火事”です。
空気が乾燥していると、火が広がりやすくなりあっという間に大火災となりかねません。
そこで“ついうっかり”で起こりがちな火災の原因と予防・対策を2回に分けてご紹介します!
今回は、家庭内火災の主な原因についてお話します。
まず、冬に欠かせないのは暖房器具ですよね!
中でも危険な物はストーブです。
室内の温度を保つために、つけっぱなしでの外出や就寝は非常に危険です。
ストーブ自体が発火するのではなく、ストーブの熱で周りにあるものが発火温度に達してしまい
火事が起こってしまいます。
また、冬になると日照時間も短く、悪天候だったりすると洗濯物を部屋干しする際に
すぐ乾くようにとストーブの上などに吊るすのも、洗濯物が落ちた時に引火する可能性があります。
エアコンなら、、、と思いますが、確かにエアコンが原因で火事が起きたというのはあまり耳にしません。
ですが、エアコンを長時間使用していると室内が乾燥し、他のもので発火が起きた際に燃えやすくなる要因でもあります。
さらに、夏と比べて冬は料理をするのに火を使う回数が増えるといいます。
部屋が乾燥している中での調理も気を付けなければなりません。
火を付けているコンロからは決して目を離さないようにしましょう。
「室内の感想に注意して!②」では、予防と対策についてご紹介します!
みなさん、こんにちわ。
残暑もまだまだ暑い日が続いていますね。
さて、前々回話をさせていた来ました労災リスクについて続きをお話します。
前回の最後に労災事故は
①設備・施設の不備
②職場環境の問題
が原因で起こると言われています。
従来から圧倒的に多いのが設備や施設の不備ですが、近年では職場環境の問題が増えてきています。
例えば、◯◯ハラスメントやメンタルヘルスといったうつ病、長時間労働などが挙げられます。
これらで気を付けなければいけないのが「労災は使用者の故意過失を問わない」という点です。
労災認定を過度におそれ、「労災隠し」をしてしまうと、刑罰の対象になるなど大きなペナルティ
があります。起きてしまった場合には、適時適切に対処することが大切です。
そこで、故意過失があるといわれないよう、あらかじめ対策を施しておくことが重要になってきます。
例えば
①危険防止措置をとる
安全衛生推進者や作業主任者などを置いたり、いわゆる4S活動(整理、整頓、清潔、清掃)
を推進するなど
②ハラスメント対策をする
研修の実施や相談場所の設置するなど
③メンタルヘルス対策をする
社内の考え方や取組方針を明確にするとともに、推進体制を充実することなど
このように様々な業種がある中で取れる対策と取りづらい対策がありますし、企業の判断も
なかなか難しいとも言えます。
しかしながら今後は企業としては、「どうしようもできなかった事故」をいかに減らせるか、
従業員が安全に働ける環境を用意できるかがカギとなってくるのではないでしょうか。
みなさんこんにちは。
先日、ネットニュースで気になる記事を見つけました。
町中でよく見かける段差スロープですが、置き方によっては違反なることがあるようです。
ホームセンターなどで簡単に購入でき、実際に家の前や駐車場で使用している人も少なくないと思います。
ですが、法的規定があり、道路法第43条(道路に関する禁止行為)第2項で、「みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞(おそれ)のある行為をすること」と、記載があるため段差スロープの設置は道路法違反になってしまう可能性があります。
便利で良かれと思って設置しても、使用しない人からすると障害物になってしまうかもしれません。
実際に、ミニバイクの大学生が段差スロープに接触して転倒し自動車にはねられるという死亡事故もあったようです。
この事故で、段差スロープを設置していた飲食店の経営者が道路法違反の容疑で書類送検されました。
また、道路に設定した段差スロープで事故が起きた場合は道路法だけでなく、民法でも設置した人に責任を問われるそうです。
民法第709条(不法行為による損害賠償)で、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」との記載があり、設置者は金銭面での責任を問われる可能性もあるということです。
そのため、敷地外の駐車などの際に段差スロープが必要な場合はその都度で設置するのが安全かつ安心でしょう。
みなさんこんにちわ。
まだまだ暑い日が続いていますね。
如何お過ごしでしょうか?
さて今回は企業の「労災リスク」についてお話したいと思います。
まずはじめに「労災」とは業務中や通勤中に起こった病気や怪我のことです。
労災認定がされた場合、労働基準法の定めによって事業者は補償責任を負うこととなります。
もし労災認定されてしまうと、最もダメージを受けるのが企業のブランドイメージです。
労災が相次げば「従業員教育を怠っている」「労働環境が劣悪」などのイメージを、取引先や世間から持たれ、契約が解消されたり株価が下落したりする恐れがあります。
労災と認められる条件は、簡単に言うとそのケガや病気が
①仕事中のものであって(業務遂行性)
②仕事が原因のものであること(業務起因性)
が必要とされています。
例えば、仕事とは無関係に休日にケガをした場合、仕事中のケガではないので「業務遂行性がない」と判断され、労災にはなりません。
また、仕事中に酒を飲んでいて転んだ場合についても、仕事が原因ではない、すなわち「業務起因性がない」ので労災の対象外といえます。
労災は、使用者の故意過失を問わず補償をする制度です。
したがって、避けようのないものもあります。
例えば、通勤中の電車が脱線した場合など、企業としてはどうしようもありません。
では、労災事故においてどのようなケースが多いのか見てみましょう。
労災事故は主に
①設備・施設の不備
例)高所からの転落事故、転倒事故、機械に巻き込まれ事故など
②職場環境の問題
例)過労死やうつ、ハラスメントなどから発生するといわれています。
近年では②職場環境の問題での労災が増えてきています。
つづきは 10/12 の記事で上げますのでご確認ください!